
【地域金融関係者向け】組織課題解決ワークショップ@オンライン・第28回
組織課題解決ワークショップ@オンライン・第28回を開催しました
2025年11月27日
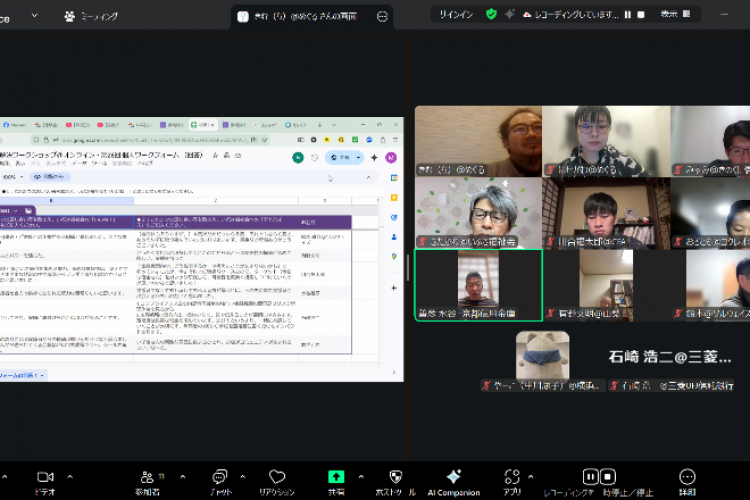
2021年から継続して開催している「組織課題解決ワークショップ@オンライン」の第28回を開催し、地域金融機関関係者を中心に8名のみなさまにご参加いただきました。
参加者の主な属性は次のとおりです。
・居住地:北海道、東京都、神奈川県、山梨県、石川県、京都府、大阪府、和歌山県
・所属:都市銀行、信用金庫、信用組合、その他
今回は、社会福祉法人いぶき福祉会(以下、いぶき)の北川雄史さんをゲストにお迎えしました。いぶきは、1984年に岐阜市で無認可の小規模作業所として誕生し、94年には市内で初めて障害分野の社会福祉法人を設立。「障害のある人と家族のねがい」から生まれ、そのねがいに丁寧に寄り添いながら、尊厳と人権を守り続けてきました。
冒頭、北川さんからいぶきの特徴や取り組みについてご紹介いただきました。法人化の際には7,000人から7,000万円の寄付を集め、以降も新たな施設を建設する際には寄付を呼びかけてきました。当初は「資金集め」が目的でしたが、多くの人のエンゲージメントを生み、「障害のある人のことを自分ごととして考える」人が増えていったといいます。
いぶきの主な財源は公的資金ですが、よりよいサービスや地域づくりに向けた費用を捻出するため、助成金や寄付募集にも積極的に取り組んでいます。今回のテーマは「金融機関と連携して遺贈寄付を推進するには?」でした。
質疑応答より(一部抜粋)
●Q:7,000人から7,000万円をどのように集めたのか? どんな人が参加したのか?
⇒当時、障害のある子どもが高校を卒業する親御さんを中心に、知人や学校の先生などへ必死に声をかけ続けた。郵便振替や募金箱を使い、人の集まる場所へ出向いては封筒を回して集めていた。今もクラウドファンディングを実施しているが、「手紙がメールに変わっただけで、やっていることは当時と変わらない」という感覚がある。
●Q:遺贈寄付や休眠預金など“託されたお金”をどう受け止め、どう伝えているのか?
⇒金額によって使い道は変わる。これまでにも遺贈に近い寄付を受けた事例があり、その際はグループホームの新設という具体的な活動を支援する形で受け取った。グループホームの数はまだ足りず、引き続き住環境整備のニーズが大きい。大規模な寄付があれば住まいの整備、小口の寄付であれば就労支援や車両購入など多様な用途がある。年次報告書などを通して、寄付者への丁寧な報告を心がけている。
また、遺贈寄付に詳しい参加者からは次の2点の助言がありました。
(1) 報告書が極めて重要。透明性の高い明朗会計やガバナンス体制の整備が必須。
(2) 広報活動の強化が不可欠。課題を知ると「見て見ぬふりができなくなる」ため、よい事例を全国へ届けることが重要。信用力はすでにあるため、情報発信を強化してメディアも動かしていけるとよいと思う。
ワーク:あなたがいぶきの役職員なら、何に取り組むか?
参加者のみなさまには、個人ワークとしてアドバイスを記入してもらいました。その一部を紹介します。
●支援者でなくても共感してもらえる方が増えれば、その先でまた支援者に出会えるかもしれないと思いました。
●(1) コンプライアンス含む内部管理統制の強化→金融機関の審査部はリスク管理体制を見るから。(2) 広報戦略の質的向上→金は少なく、質で伝えることが遺贈には効きます。富裕層は良質な物語を求めています。助けてというより、一緒に共感してもらうことが大切です。
●アドバイスはできません。信組の人間としてとてももどかしい気持ちです。でも理解ある金融人や一緒に動いてくれる金融機関もあると信じたいです。
北川さんからのメッセージ
「さまざまなことをお伝えでき、私自身の自信にもつながりました。信用を高めることや、もう一歩外の方たちとあえて組むことの大切さを感じました。」
参加者アンケートより(一部抜粋)
●みなさんの志に触れられて幸せな気持ちになりました。
●やはり現場の話を生で聴くことが大事だと思いました。
●久しぶりに参加して、また、勉強になることがありました。なるべく時間をつくり、参加します。
次回は2026年2月に開催予定です。みなさまのご参加をお待ちしています。
参加者の主な属性は次のとおりです。
・居住地:北海道、東京都、神奈川県、山梨県、石川県、京都府、大阪府、和歌山県
・所属:都市銀行、信用金庫、信用組合、その他
今回は、社会福祉法人いぶき福祉会(以下、いぶき)の北川雄史さんをゲストにお迎えしました。いぶきは、1984年に岐阜市で無認可の小規模作業所として誕生し、94年には市内で初めて障害分野の社会福祉法人を設立。「障害のある人と家族のねがい」から生まれ、そのねがいに丁寧に寄り添いながら、尊厳と人権を守り続けてきました。
冒頭、北川さんからいぶきの特徴や取り組みについてご紹介いただきました。法人化の際には7,000人から7,000万円の寄付を集め、以降も新たな施設を建設する際には寄付を呼びかけてきました。当初は「資金集め」が目的でしたが、多くの人のエンゲージメントを生み、「障害のある人のことを自分ごととして考える」人が増えていったといいます。
いぶきの主な財源は公的資金ですが、よりよいサービスや地域づくりに向けた費用を捻出するため、助成金や寄付募集にも積極的に取り組んでいます。今回のテーマは「金融機関と連携して遺贈寄付を推進するには?」でした。
質疑応答より(一部抜粋)
●Q:7,000人から7,000万円をどのように集めたのか? どんな人が参加したのか?
⇒当時、障害のある子どもが高校を卒業する親御さんを中心に、知人や学校の先生などへ必死に声をかけ続けた。郵便振替や募金箱を使い、人の集まる場所へ出向いては封筒を回して集めていた。今もクラウドファンディングを実施しているが、「手紙がメールに変わっただけで、やっていることは当時と変わらない」という感覚がある。
●Q:遺贈寄付や休眠預金など“託されたお金”をどう受け止め、どう伝えているのか?
⇒金額によって使い道は変わる。これまでにも遺贈に近い寄付を受けた事例があり、その際はグループホームの新設という具体的な活動を支援する形で受け取った。グループホームの数はまだ足りず、引き続き住環境整備のニーズが大きい。大規模な寄付があれば住まいの整備、小口の寄付であれば就労支援や車両購入など多様な用途がある。年次報告書などを通して、寄付者への丁寧な報告を心がけている。
また、遺贈寄付に詳しい参加者からは次の2点の助言がありました。
(1) 報告書が極めて重要。透明性の高い明朗会計やガバナンス体制の整備が必須。
(2) 広報活動の強化が不可欠。課題を知ると「見て見ぬふりができなくなる」ため、よい事例を全国へ届けることが重要。信用力はすでにあるため、情報発信を強化してメディアも動かしていけるとよいと思う。
ワーク:あなたがいぶきの役職員なら、何に取り組むか?
参加者のみなさまには、個人ワークとしてアドバイスを記入してもらいました。その一部を紹介します。
●支援者でなくても共感してもらえる方が増えれば、その先でまた支援者に出会えるかもしれないと思いました。
●(1) コンプライアンス含む内部管理統制の強化→金融機関の審査部はリスク管理体制を見るから。(2) 広報戦略の質的向上→金は少なく、質で伝えることが遺贈には効きます。富裕層は良質な物語を求めています。助けてというより、一緒に共感してもらうことが大切です。
●アドバイスはできません。信組の人間としてとてももどかしい気持ちです。でも理解ある金融人や一緒に動いてくれる金融機関もあると信じたいです。
北川さんからのメッセージ
「さまざまなことをお伝えでき、私自身の自信にもつながりました。信用を高めることや、もう一歩外の方たちとあえて組むことの大切さを感じました。」
参加者アンケートより(一部抜粋)
●みなさんの志に触れられて幸せな気持ちになりました。
●やはり現場の話を生で聴くことが大事だと思いました。
●久しぶりに参加して、また、勉強になることがありました。なるべく時間をつくり、参加します。
次回は2026年2月に開催予定です。みなさまのご参加をお待ちしています。
本プロジェクトは、ログインしてお気に入り追加や支援をすると、「活動報告」更新時に通知メールが届きます。
また、支援者による支援の申し込みが完了した時点で、凸と凹登録先が支援金の提供を受ける契約が成立するものとします。
1,000 円
配送方法:メール
(1) 「組織課題解決ワークショップ@オンライン」参加者限定のFacebookグループページへのご招待
2,000 円
配送方法:郵送
(1) 「組織課題解決ワークショップ@オンライン」参加者限定のFacebookグループページへのご招待
(2)『お金の地産地消白書2020』1冊



